これは札幌の地に新たに誕生した、あるサッカーチームの監督の、戦略ノートの抜粋という形をとった、私なりの『コンサドーレ観戦記』であります。『観戦記』といっても特定の試合についてではなく、去年と今年、コンサドーレを観戦しながら思ったことや、これまで北海道のスポーツについて考えていたことなどを一緒くたにまとめてみたのでした。
もちろんこれはすべてフィクションであり、文中、一人称で書かれているフェルナンデス監督なる架空の人物は、言うまでもなくコンサドーレのウーゴ・フェルナンデス監督とはまったく別人物であります。また文中、現実の選手を連想させる表現がでてきますが、これも架空の物とお考えください。
(記事:塩らーめん)
フェルナンデスの戦略ノート 1
私が札幌のチームの監督を引き受けることが決まったとき、私の脳裡に日本地図のシルエットが瞬間的に浮かびあがり、なにか重要な啓示を私に与えたような気がした。今、私のノートの一頁目を開いてみると、最初の行には書き殴りの文字が並んでいる。それはきっと曖昧模糊としたその啓示を、なんとか言葉に表そうとして苛立ちに紛れて綴ったものであったに違いなかった。そこにはこう書かれていた。
『日本における札幌(北海道)の地理的・気候的特異性』
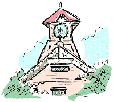 私はその昔、東京でコーチをしていた経験があるから、札幌が日本のどこにあるか、どういう街であるか、多少なりとも知らないではなかったのだ。もっともだからといって、私がこれから為すべきサッカーにそれがどれほど反映されるのか、或いは反映されるべきなのか、私の頭にはまだ明確な形としてあったわけではなかった。
私はその昔、東京でコーチをしていた経験があるから、札幌が日本のどこにあるか、どういう街であるか、多少なりとも知らないではなかったのだ。もっともだからといって、私がこれから為すべきサッカーにそれがどれほど反映されるのか、或いは反映されるべきなのか、私の頭にはまだ明確な形としてあったわけではなかった。
日本に着き、さっそくチームに合流し、宮崎及び豪州合宿において、選手の個性と特性を掌握していくにつれ、そしてGMやコーチィング・スタッフ等からJFLの現況をヒアリングするにつれ、白紙だったチームの方向性と完成予想図がしだいに明瞭になってきたのだった。
しかし次のページを開く前に、私が来日直後、直面したある質問について言及しておこう。それへの回答が私の戦略を語る端緒になってくれるはずである。
その質問とはこうである。
「本当に札幌のチームで勝ち抜いていけるのか?」
日本のスポーツ界に浸透している常識として、夏期屋外スポーツにおいての『北国のチームのハンディ』というのがあるらしい。冬期間の練習不足からくるひ弱さ、不慣れな高温多湿の気候下での自滅的連戦連敗、等々が常識たらしめている要素で、もろもろの結果がそれを裏付けているという。上述の質問はその常識からなされたものなのだろう。その常識はさらに『北国チームの弱小性』という、言葉にはされないもうひとつの意味も含まれているらしいのだ。
しかし私は分析の結果、それはあくまで日本のスポーツ界をリードしてきたアマチュアスポーツ界に内在する特殊事情が影響していると結論を下した。たとえばそれらの全国大会の多くが大会方式に採用している、一ヶ所に集まって一回戦から決勝戦までを数日以上の期間のなかに集中して消化するという、一種のセントラル方式にも一因があろう。
セントラル=中立といっても、開催地が経済力の集積している東京を中心とした関東圏と、大阪を中心とした関西圏に集中するこの『偽セントラル方式』においては、ホームタウン/エリアで試合のできる関西・関東のチームが、完全アウェー状態の北国チームから高い勝率をあげるのは科学的統計学上の当然の帰結で、また人口の多いそれらのエリアからは出場チームがたくさんあるわけだから、彼ら彼女らの実力が一見抜きんでているように見えるのもこれまた当然の結果なのだ。
この場合、『北国のハンディ』というよりむしろ『北国チームの犠牲』というほうが正確だろう。
不思議なのは、この明白な不平等によって不利益を被っているはずの北国のスポーツ選手やスポーツファン、スポーツ関係者らが、この不平等な現実にじつに従順であるという事実である。ひょっとすると、彼ら彼女らは、経済的問題以外にも、中央人たち(アマチュアスポーツ組織、スポンサー、マスメディア、ファン等)がその不平等によって生じる自らの権益を既得化せんと捻出したとしか思われない幾つかの策略に、すっかり洗脳されているのかもしれない。
策略の代表例としてあげられるのは『開催地の聖地化』(甲子園、花園、国立、神宮、東京ドーム、代々木等)で、現状では、聖地の移動はその大会の存在意義すら消滅させかねない事項にまで成り上がってしまっている。
 もちろん中央人たちは自分たちの大切なイベントが『犠牲』のうえに成立しているとは考えられたくも、また考えたくもないので、『北国のハンディ』という言葉を捏造し、それは体制が改善すべき課題ではなく、自ら乗り越えるべき課題なのだと徹底するわけだ。だから『ハンディ』を克服して北国チームが勝利を得た(それは統計上一定の確率で出現するが、50%には程遠い割合である)暁には、過剰な感動のドラマを演出して称賛することにより『犠牲』の代償とし、アンフェアな現実を合理化するのである。
もちろん中央人たちは自分たちの大切なイベントが『犠牲』のうえに成立しているとは考えられたくも、また考えたくもないので、『北国のハンディ』という言葉を捏造し、それは体制が改善すべき課題ではなく、自ら乗り越えるべき課題なのだと徹底するわけだ。だから『ハンディ』を克服して北国チームが勝利を得た(それは統計上一定の確率で出現するが、50%には程遠い割合である)暁には、過剰な感動のドラマを演出して称賛することにより『犠牲』の代償とし、アンフェアな現実を合理化するのである。
こうして『北国チームのハンディ』は公正な科学的視点を無視したまま、不治の病として半永久的に日本のスポーツ界に定着していくのである。
これらを、日本のスポーツ文化の未成熟さと一笑に伏すのも可能だし、所詮(建前上は)勝敗を第一の目的としないアマチュアスポーツ固有の問題と考えればいいのかもしれないが、重要なのは、『北国チームのハンディ=弱小感』が常識を通り越して迷信となり、アマチュアの境界からプロスポーツの世界にまでひとり歩きしてきているという事実である。その強固さからみて、それは、どこの国にも存在する文化的社会的中央集権構造の生み出す、『辺縁地域への軽視・蔑視』と、その表裏で存在する『辺縁地域に根付くコンプレックス』とに結びついてもいるのだろう。だとしたら事は重大だ。ゲームに有形無形の影響を与えるほど、呪縛力の大きい迷信と見るべきだろう。
自分にハンディが存在するという精神的劣位が支配しているチームと、相手にハンディが存在するという精神的優位が支配しているチームが戦うなら、そのハンディはたとえそれが錯誤が生産したものであっても、現実のものといえる。
ただでさえ、サッカー界の常として、トップリーグを狙うといっても、2部のチームには、トップリーグで失敗者の落胤を押されたり、加齢という能力減退の宣告をされたプレーヤーが多いのだ。加えて我がチームには、過渡期にある日本のサッカー界の特殊事情が生む、クラブ経営の挫折によって放出されたプレーヤーまでいるのである。ともすれば精神的劣位に陥りがちなそれらのプレーヤーたちのメンタリティのなかに、それ以上の要因を消化する余裕はない。
一年間の長く厳しいプロスポーツのリーグ戦を戦う場合、どんな些細なハンディも不要であって、排除しなくてはならない。それが昇格をかけた、クラブの存亡すらかけた戦いならなおさらのことだ。
プレーヤーの身体にしみ込んだ迷信を排除するにはどうすればいいのだろう?
こうした状況とは違うかもしれないが、面白い例がある。1993年、カタールで開催されたワールドカップ米国大会アジア最終予選の日本-韓国戦だ。試合開始直前、まだ控え室で待機中の選手たちの前で、H.オフト日本代表監督(当時)は配られてきた韓国チームのスターティングメンバーシート表をビリビリと破り捨て、檄を飛ばしたのだという。
日本チームに根付いていた韓国コンプレックスを払拭するための過剰なまでのパフォーマンスといえる。
既成概念を打破するためにはカリスマ性を備えたリーダーの戦略が必要なのかもしれない。私が、我がチームの苦悩するプレーヤーたちに常時吹き込まなければならない言辞とは単純で過激で強気であるべきなのだ。或いはナンセンスであってもかまわない。
「お前たちはいちばん強い」「すべて決勝戦だと思って戦え」「男らしいプレイをしろ」、そして「何が何でも勝利しろ」
敗戦のあとでも動揺してはいけない。弱気こそこのチームには罪悪だ。
「こんな敗戦は小石につまづいたようなもの。だったら小石を蹴飛ばしてしまえ」「PK戦の負けは負けではない。だからこのゲームには負けていない」 精神的劣位を一刻でも感じさせてはいけない。
ゲーム中の派手なパフォーマンスもむろんその一環である。拳を振り回し、大声を張り上げ、対戦チームの監督と怒鳴りあい、椅子を蹴りあげ、ボールを蹴飛ばし、怒り、泣き、笑い……できるかぎりのパフォーマンスがプレーヤーたちを鼓舞し、愚劣な迷信の呪縛から解放するのだ。
 プレーヤーをとりまく環境(家族、スタッフ、クラブ、サポーター、地方マスメディア等)を利用しない手はない。それらを取り込み、大きなランニング(追い風)とすることができればプレーヤーの攻撃的なモチュペーションを長期間にわたり維持していくのに有利だろう。
プレーヤーをとりまく環境(家族、スタッフ、クラブ、サポーター、地方マスメディア等)を利用しない手はない。それらを取り込み、大きなランニング(追い風)とすることができればプレーヤーの攻撃的なモチュペーションを長期間にわたり維持していくのに有利だろう。
幸い状況は味方していた。北海道では我がチーム以外にプロスポーツチームはなく、加えて我がチームこそが北海道における歴史上初めてのプロチームなのだ。さしたる困難もなく、それらは思い通りの盛りあがりを見せてくれた。だから私はささやかなひとつの戦略を画策するだけでよかった。『ファミリー』という『流行語』をつくり、プレーヤーと環境の一体化をより強固になるよう宣伝したのだ。
言葉がひとつの集団において流行語になるということは、その集団に同一の精神的・心理的状態が存在する、ということではあるまいか? であるなら流行語の浸透と普及の作業が集団における同一の精神的・心理的状態の形成とはいかないまでも、調整やきっかけには十分なりうるのではあるまいまか? でなければ様々な媒体を通じて流される商業的コマーシャルの反復に、あれほど巨額な資金が投入されるわけもない。
言葉の持つ力は今更言うまでもなく絶大だ。
NBAやJリーグが既存のスポーツ団体とは違う用語を普及させることによって自己の存在を明確にしようとしたように、狂信的なオカルト新興宗教団体が、一般社会と徹底的に差別化された単語を用いることで集団をひとつにまとめていくように、私の言葉が『流行語』になれば、プレーヤーとその環境の同一化を継続させるのに貢献するはずである。
この『ファミリー』は私のゴッドファーザーにも似た風貌や言動や挙動とリンクして完全とはいかないまでも『流行語』となっている。『流行語戦略』は機能している。
非科学的な迷信というウィルスに侵されていたメンタリティは初期化された。それぞれの経緯で『辺縁』の北国チームに『来てしまった』プレーヤーたちのメンタリイティも初期化された。今や彼らは戦闘意欲を漲らせたまったく新しいプロフェッショナルなプレーヤーとして再生した。ライバルチームのプレーヤーたちと同じスタートラインに、『来てしまった』のではなく、『集い、立ちあがった』のだ。
話はずいぶんメンタルな面に偏ってしまったようだ。次にフィジカルな側面から『札幌の特異性』を見てみよう。どこからにしよう? このあたりからにしてみようか。
……しかし私は分析の結果、それはあくまで日本のスポーツ界をリードしてきたアマチュアスポーツ界に内在する特殊事情が影響していると結論を下した。たとえばそれらの全国大会の多くが大会方式に採用している、一ヶ所に集まって一回戦から決勝戦までを数日以上の期間のなかに集中して消化するという、一種のセントラル方式にも一因があろう。……
……プロはもちろん違う。多くの資金をつぎこみ、かかわる人間の人生をかけて争われるプロの戦いがさすがにこんなアンフェアではお話にならない。
厳格なホーム・アンド・アウェー方式であれば、そしてサッカーのように一週間に1ゲーム、それもアウェーが一週おきで、遠征といっても前日の午後に現地入りし、試合当日に2時間弱の試合をし、当日夜、もしくは翌日朝、帰還するというせいぜい丸二日、敵地に滞在するだけのスケジュールであれば何も問題はない。(2試合以上、5日以上の遠征であれば影響はあるだろう。しかしそのスケジュールは稀だろう)ワンハーフ45分間というタイムスケールは心身の集中力が持続する範囲内と考える。純粋なアウェーの不利(サポーターの有無、グランド条件の不慣れ等)以外の不利は札幌にはなく、『北国のハンディ』は消滅するだろう。
いや、むしろサッカーにおいては『北国チームの優位性』が私には自明に思える。本州の夏が暑ければ暑いほど札幌にとって有利に展開していくと確信している。
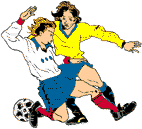 なぜなら日本のサッカーシーズンの大半を占める日本の夏は、スポーツにとって厳しく苛酷な自然環境だからだ。在日アフリカ、在日中東、在日東南アジアの人々に尋ねてみるがいい。彼ら彼女らは口をそろえて自国の夏より日本の夏のほうが厳しいことを主張するだろう。キンシャサやリヤドやクアラルンプールよりも厳しい環境でトレーニングし、試合をしていかなければならない本州以南のチームと、冷涼で梅雨もなく、台風の影響を日本で最も受けにくく、日照率も高い札幌でそれができる我がチームとでは、体力・技術・戦術・戦略トレーニングの消化率にまず決定的といってもいい差が生じるだろう。必然的にフィジカル面でも開きがでてくるだろう。本州チームの夏の合宿先が菅平や北海道に多く集まっていることを思い出してほしい。涼しいところでは体力の消耗は低く、また回復も早い。ゆえにトレーニングの効率もいい。持久力にとんだ強靭なサッカー選手の肉体を作るのに適しているのだ。
なぜなら日本のサッカーシーズンの大半を占める日本の夏は、スポーツにとって厳しく苛酷な自然環境だからだ。在日アフリカ、在日中東、在日東南アジアの人々に尋ねてみるがいい。彼ら彼女らは口をそろえて自国の夏より日本の夏のほうが厳しいことを主張するだろう。キンシャサやリヤドやクアラルンプールよりも厳しい環境でトレーニングし、試合をしていかなければならない本州以南のチームと、冷涼で梅雨もなく、台風の影響を日本で最も受けにくく、日照率も高い札幌でそれができる我がチームとでは、体力・技術・戦術・戦略トレーニングの消化率にまず決定的といってもいい差が生じるだろう。必然的にフィジカル面でも開きがでてくるだろう。本州チームの夏の合宿先が菅平や北海道に多く集まっていることを思い出してほしい。涼しいところでは体力の消耗は低く、また回復も早い。ゆえにトレーニングの効率もいい。持久力にとんだ強靭なサッカー選手の肉体を作るのに適しているのだ。
(大量の積雪によってグラウンドを使用できない冬の存在は合宿地の移動によって対応できる。ホームスタジアムを使えない春先の数試合はたしかに不利だが、それもドームスタジアムなどの整備によりいずれ解消できる)
或いは人はこう言うかもしれない。 「たしかに札幌は涼しくコンディションの調整や厳しいトレーニングには適しているかもしれない。しかし試合はホームばかりでプレイされるわけではない。一週間おきとはいえ、最高気温で、ときに10度以上差がある本州でのアウェー戦を半分はこなさなくてはならないのだ。それはやはり不利と言わないわけにはいかないだろう。なんといっても本州チームはその酷暑に順化しているのだから」
本州チームは暑さに慣れている、というのは表現としてまちがっているわけではない。たしかに慣れている。しかし慣れているのと強いのとは別だ。どんな人間でも人間であるかぎり、暑さのなかでプレイすればどんどん体力を消耗していく。どんな肉体をもってしてもそれは避けられない。ただし、基礎体力が10の選手と8の選手を比べれば8の選手が先にバーストするのは明らかだろう。人間の基本的な身体能力、とくに同民族間の身体能力には居住地域によって有意の差は存在しない。あるのは個人差と的確なトレーニングによって身につけられるプラスアルファの程度の差、だけであって、気温が高くなればなるほど、その基礎体力の優劣が勝敗を左右してくるのであり、では優越する基礎体力を獲得する可能性が高いのは酷暑の本州かといういうとそうではなく、冷涼な札幌であるにちがいないのだ。
もし本当に勝率に誤差以上の差がでるほど本州チームが暑さを味方にしているというなら、彼らはその暑いなかに適応した独自のサッカースタイルやトレーニングスタイルを進化させていなければならない。だがそういうことはほとんどない。彼らのしているサッカーは温暖で湿度の低い条件下でなされる、ごく普通の組織的サッカーのスタイルとそれを完成するためのトレーニングで、具体的に言えばイングランドや、ドイツを筆頭にした中欧のサッカーである。
だが、それらの国々のサッカーシーズンの平均気温と湿度は本州のそれとははっきりとした差が存在する。むしろ英・中欧と近似しているのは札幌である。ミュウヘンと札幌が共にビールの優秀な産地であるのは偶然ではない。北海道の芝が日本で最も欧州に近いとするラクビー関係者の証言もその証明だ。
私の祖父は言っていた。
「同じ草が生え、同じ花が咲いている土地の
サッカーはどこも似ているものだ」
札幌が英・中欧スタイル(つまり日本の標準のスタイル)を採用するのは気候的には無理がなく、本当は本州チームにこそ無理がある。
長いシーズンを戦いぬくうえで、相手よりフィジカルや戦略面で無理があれば致命的だ。最終成績に明確な差が生じるだろう。迷信の呪縛などとは比較にならないほどの決定的な差である。
本州チームがこの現実に気付かず、現在と同様のスタイルに固執しつづけるかぎり、札幌も彼らと同じスタイルを採用するのは賢い選択といえる。
 だからといって、ここで彼らを怠慢で創造性のない連中だと決め付けるのは行きすぎかもしれない。なぜなら彼らはこれまで北海道のプロチームと対戦した経験がないのだから。本州のチーム同士の対戦ばかりであれば、皆同等に疲弊・消耗していくのだからそれによって勝敗が左右されるなどということは顕在化しない。『みんなで夏バテすれば恐くない』のである。
だからといって、ここで彼らを怠慢で創造性のない連中だと決め付けるのは行きすぎかもしれない。なぜなら彼らはこれまで北海道のプロチームと対戦した経験がないのだから。本州のチーム同士の対戦ばかりであれば、皆同等に疲弊・消耗していくのだからそれによって勝敗が左右されるなどということは顕在化しない。『みんなで夏バテすれば恐くない』のである。
今後、我がチームが活躍することによって、それが証明されることになるだろう。
『札幌の地理的・気候的優位性』
これこそが我がチームがライバルチームに圧倒的な差を付けるアドバンテージであり、財産であると私はノートの次の頁に書き記している。サッカーというゲームがその土地の風土や気候、民族性によってそれぞれ独特のスタイルを持つことはよく知られている。代表的な例が『欧州型』と『南米型』だ。しかしこれは両地域の交流が活発になるにつれ、またサッカー理論が近代化されるにつれ、垣根が消滅し融合してきているとも言われる。しかしそれでもなお、その地域の特性を無視してチーム作りをすることにはリスクがともなうと考えるべきだ。そしてその特性が財産であると確信できるならそれを最大限に利用しない指揮官は愚かだろう。
『札幌の地理的・気候的優位性』……
『特異性』とあったところが『優位性』に変わっている。しだいに我がチームの姿が全貌を表しつつあるようだ。
(以上記事:塩ラーメンさん)
